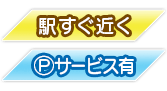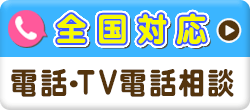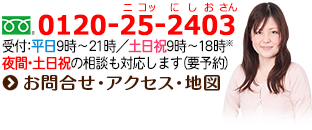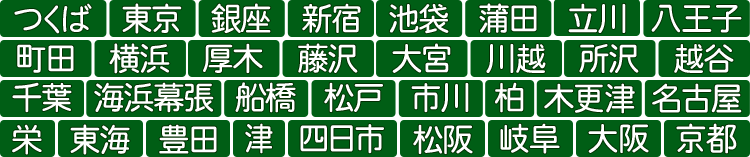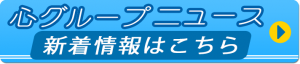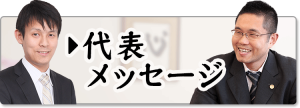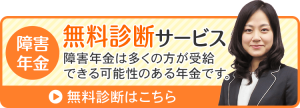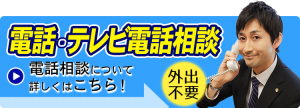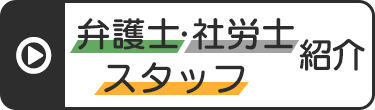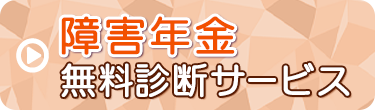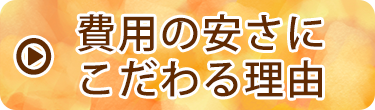心筋梗塞で障害年金を受け取れる場合
1 心筋梗塞で障害年金を受け取れる場合がある
心筋梗塞を発症した場合、心疾患による障害として、障害年金を受給できる可能性があります。
以下では、心筋梗塞で障害年金を受給できる場合について、ご紹介いたします。
2 心筋梗塞の認定基準と具体例
心疾患による障害認定基準には、各等級に該当する障害の程度が包括的にさだめられており、認定要領の虚血性心疾患の項目に、心筋梗塞で等級に該当する場合が具体的に例示されています。
【1級】
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が他の1級の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活を独力で送ることが不可能な程度のものが1級に該当します。
具体的には、病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、身のまわりのことができず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる場合が挙げられます。
【2級】
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が他の2級の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものが2級に該当します。
具体的には、①心電図等の検査で異常所見が2つ以上あり、かつ、②軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状が出てくるもので、かつ、③身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったものに該当するものか、あるいは、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているものに該当する場合が挙げられます。
【3級】
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものが3級に該当します。
具体的には、①心電図等の検査で異常所見が1つ以上あり、かつ、②心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、③歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているものに該当するか、あるいは、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるものに該当する場合が挙げられます。
3 心筋梗塞で障害年金を受けとる場合のポイント
上記のとおり、心筋梗塞の等級認定においては、検査結果、症状の内容や程度、日常生活や就労の状況がチェックされますので、日ごろから、必要な検査をしっかり受けていただき、主治医の診察の際に症状の内容と程度、日常生活状況や就労状況を詳細にお話いただくことが重要です。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金のオンライン相談|自宅から無料で相談できます(全国対応)
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できますか
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 学習障害で障害年金を受け取れる場合
- 網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 脳出血で障害年金がもらえる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 心筋梗塞で障害年金を受け取れる場合
- 肝がんで障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金を受給することのリスクはあるのか
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
0120-25-2403