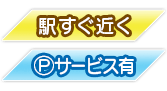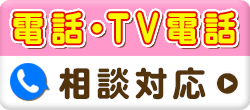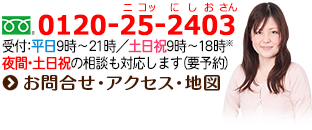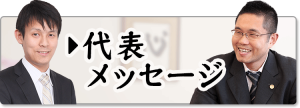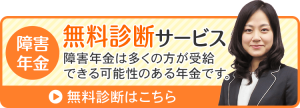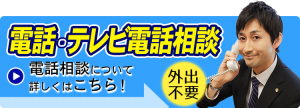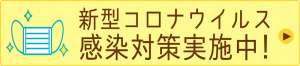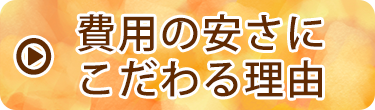障害年金で必要な書類
1 診断書
診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。
いろいろな症状を併発している場合は2種類、3種類の診断書を提出する必要がでてきます。
診断書の内容は、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。
診断書を作成することができるのは医師ですが、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。
主治医とコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。
診断書のひな形は日本年金機構のホームページで公開されています。
2 病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書(申立書)は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価して行政にアピールできるのは、この申立書以外にありません。
そのため、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように、できる限り具体的に作成する必要があります。
診断書との整合性が必ず求められますので、矛盾が生じないように注意が必要です。
3 受診状況等証明書
受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得する証明書類のことをいいます。
初診日を確定するためのものなので、「初診日証明」ともいわれます。
ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっているため、初診時の医療機関で診てもらった時が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していたりした場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。
その場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」とともに、医療保険の給付にかかる記録などの初診日を証明・推定できる書類を付けて提出します。
請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。
4 年金請求書
年金請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類です。
障害年金の請求は、この年金請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。
年金請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
0120-25-2403