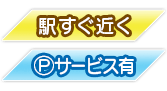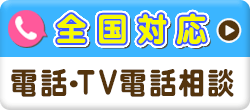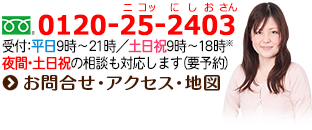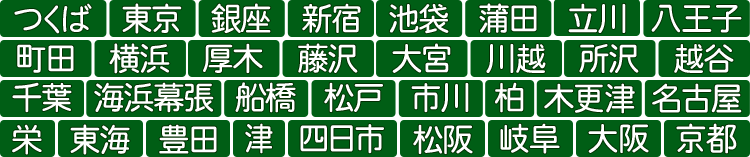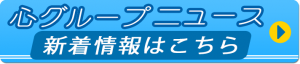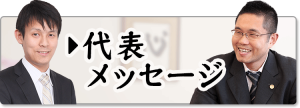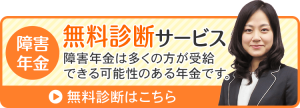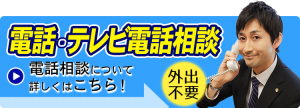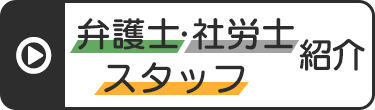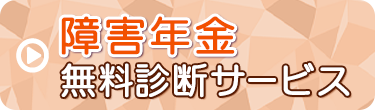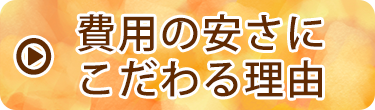肝がんで障害年金を請求する場合のポイント
1 肝がんとは
肝がんとは肝臓にできるがん(悪性新生物)の総称です。
肝臓は、「沈黙の臓器」とも呼ばれており、がんや炎症があっても、ほとんど自覚症状がないことも多いです。
進行していくと腹部のしこり、圧迫感、痛みなどの症状が生じ、さらに進行すると、肝不全の症状として腹水やむくみ、黄疸、肝性脳症が起こってきます。
肝がんで障害年金を申請する際には、検査の数値や症状に合わせて適切な診断書を選択することがポイントになります。
2 肝がんと障害年金
肝がんにより、日常生活に制限が生じたり、労働能力に制限を受けるような場合には、障害年金の対象になります。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると、肝がんに対しては、肝疾患による障害の認定要領及び悪性新生物による障害の認定要領によって認定するとされています。
3 肝疾患による障害の認定要領
肝疾患による障害の認定要領では、一般状態区分(障害がその人の全身の状態にどのように現れ、日常生活や労働がどの程度の制限を受けているかを5段階に区分したもの(注))と各種検査項目(血清総ビリルビン、血清アルブミン、血小板数、プロトロンビン時間)の異常の有無や臨床所見(腹水、脳症の程度)から判断するとされています。
4 悪性新生物による障害の認定要領
認定要領によると、悪性新生物による障害は、悪性新生物そのものによって生じる局所の障害、悪性新生物そのものによる全身の衰弱又は機能の障害、悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害の3つに区分されるとされています。
悪性新生物によって生じる局所の障害とは、特定の部位に障害が残った場合です。
肝がんの場合には、肝臓に障害が生じた場合で、これは肝疾患による障害の認定要領にしたがって判断されます。
これに対して、悪性新生物そのものによる全身の衰弱とは、がん細胞が増殖して身体が弱った状態、悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害とは、抗がん剤などの副作用による身体が弱っている状態です。
これらについては、全身の衰弱や機能の障害、倦怠感等の程度や、一般状態区分表のどこに該当するか等を総合的に考慮して、障害の程度が判断されます。
5 肝がんで障害年金を請求する場合のポイント
このように肝がんについての障害年金の申請は、肝疾患の障害および悪性新生物による障害の二つの方向から審査されることになります。
肝疾患の障害については、腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書が使用され、悪性新生物による障害については血液・造血器その他の障害用の診断書を使用することになります。
そのため、各種検査項目の異常の有無や臨床所見の有無、全身の衰弱や倦怠感の状態等から、どのような診断書を作成してもらうかが、肝がんで障害年金を申請する際のポイントになります。
どのような場合にどの診断書を書いてもらうかは、個別の状態、症状によります。
詳しくは、弁護士や社会保険労務士等にご相談ください。
(注)一般状態区分表
| 区分 | 一般状態 |
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できますか
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 学習障害で障害年金を受け取れる場合
- 網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 脳出血で障害年金がもらえる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 心筋梗塞で障害年金を受け取れる場合
- 肝がんで障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金を受給することのリスクはあるのか
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
0120-25-2403